2025/07/15 00:39
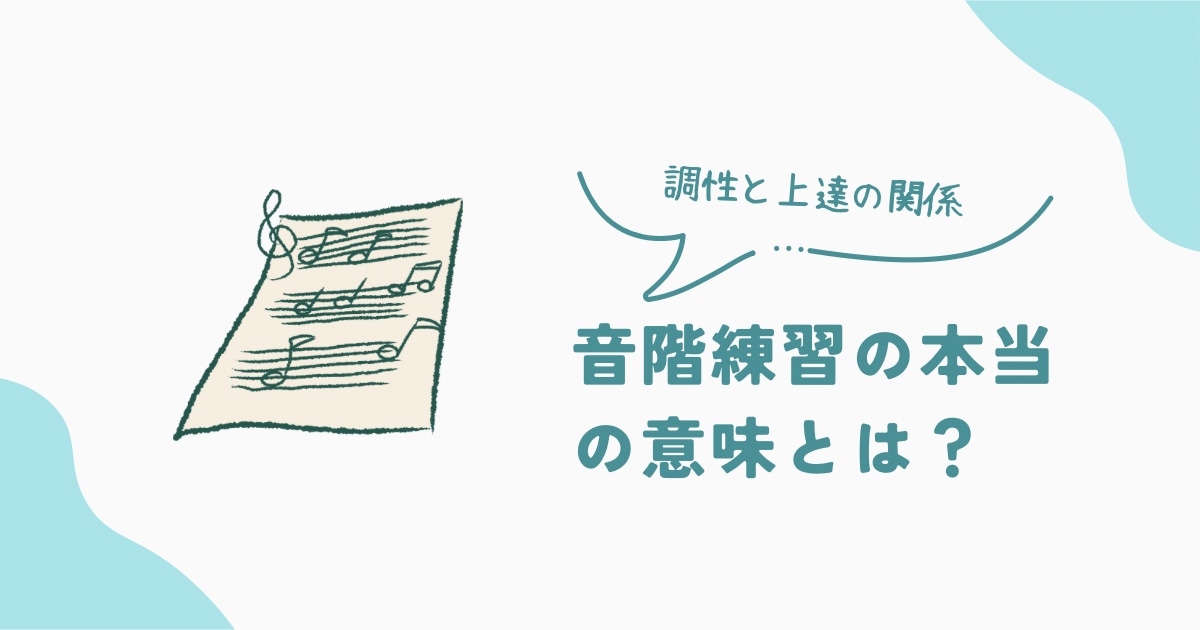
こんにちは、たてのフルート教室です!
「毎日スケール(音階)を練習しましょう」と先生に言われたこと、ありませんか?
でも、「同じような音の並びを繰り返して、何の意味があるの?」と思った方もいるかもしれません。
実はこの音階練習、フルート上達の土台作りとしてとても大切なんです。
今日はその理由を、楽典(音楽理論)とともに、やさしく解説します。
音階=調性の「言葉」を覚えること
音楽には「調性(ちょうせい)」というルールがあります。たとえば「ハ長調(C dur)」や「ト長調(G dur)」などがそれにあたります。これらの調には、それぞれ決まった音の並びがあり、私たちがよく耳にするメロディは、ほとんどがこの「音階」をもとに作られています。
音階練習をすることで、その「調の特徴」を体で覚えていくことができます。たとえば、G durでは♯が1つ(ファがシャープ)ついていますね。この音を無意識に押さえられるようになることが、読譜力や演奏の安定につながるのです。
音階は「音の地図」
どの音をどこで吹くかを覚えるだけでなく、音と音の間の距離(音程)を感覚的に理解することも大切です。これは、後に難しい曲を吹くときに、「このメロディは〇〇調っぽいな」と気づく力にもなります。
また、スケール練習を通して、息のコントロールや音のつながり(レガート)、タンギングの練習も自然とできるので、一石三鳥の練習なのです。
毎日少しずつでOK
全部の調を毎日やろうとすると大変ですが、1日1つの調をゆっくり丁寧に練習するだけでも、効果はしっかり現れます。
無理なく、でも「今日はこの調」と意識することで、あなたのフルート演奏は、確実に一歩ずつ前進していきますよ。
「なんとなく」から「わかって練習する」へ。
今日から、音階練習をちょっと好きになってもらえたら嬉しいです。
